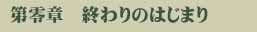
三、
6.
その瞬間、カイルが後方に吹っ飛ばされた。
ふっ飛ばしたのは、カイルの髪を引っつかんでいた男。
男…、テンドウはカイルを後方に投げ飛ばし、その空いた腕で己の心臓めがけて放たれたダガーを受け止めた。
「どういうつもりだ」
「どういうつもり…ねえ。ま、あいつ曰くで言わせてもらうなら、理由はない、らしいぜ」
「………」
「あんた流儀で言わせてもらうなら、気まぐれ、でもいいんだけどな」
そう言ってラフィは始めにカイルが防いだときに叩き落された投げナイフを拾いあげると、枷と枷の間にある鎖を、ナイフをコテのようにつかい、千切り落とす。足も同じようにした。
そうして、自由になった手足をめいっぱい広げると、伸びをし、柔軟をはじめ、屈伸した後、ようやく黒尽くめの男にラフィは向かい合った。そして、投げナイフを握りこむと不敵にテンドウを見た。
「ようするに、俺が相手だ。こいよ、頭領」
7.
「くだらん」
一言切り捨てると、テンドウは格子越しにラフィをにらみつけ、投げナイフを繰り出す。
細い隙間から繰り出されるナイフは的確にラフィの急所をめがけるが、ラフィもすばしこい足で、それをよけていく。
「おっと、わりぃなわざわざ武器を増やしてくれて」
「………」
軽口を叩いて、手に持っていた方の投げナイフをテンドウに投げつける。
しかし、当然のようにそれは相手のダガーによって打ち落とされた。
「くだらん。貴様がいくら優秀な暗殺者であろうと、剣もなく、牢屋越しで俺が倒せると思ってるのか」
「まあ…、無理があるよな、実際」
ラフィは足で落ちている投げナイフを一つ蹴り上げ、手に収めながらテンドウに答える。確かに、自身の得意であった剣も、あたりまえだが取り上げられ、鎖を引きちぎり多少自由が利くといっても、所詮は牢の中。どうやっても己とテンドウとの間合いを詰めることは出来ない。
「だが、あんただから有利な点が1つある」
そう言って、再び投げナイフを放つ。今度はテンドウの眼球を目がけてだ。
しかしそれを、再び弾き落とす。が―――…
「そっちは囮、…っだ!」
ラフィは眼球に放った投げナイフの後に続けて、足元にあったもう一つのナイフを蹴り上げ、テンドウの腰もとに目がけて飛ばした。
眼球に放たれた投げナイフが死角になり、腰に飛ばされたナイフがその男が腰もとにくくりつけてあった小袋に命中する。
「他人ならいざ知らず、規則一辺倒のあんたなら、ぜったいにそこに入れているはずだぜ、煙幕玉をな」
「なに?」
闇の中で男の下げていた袋が、ラフィのナイフにより爆発した。
もともと煙幕用のための物だと察している。爆発の規模よりもはるかに殺傷力が弱い、そのため、テンドウを倒せるような代物ではない。
だが、白濁の闇の中で、ラフィは静かに言った。
「有利な点が俺には2つあったよ」
白濁の煙幕は、どこからかの風穴に吸い込まれるようにして次第に薄れていく。
「一つは、俺があんたを知っていたこと、ああこれはさっき言ったか」
薄れてきた闇のなかで、ラフィは視界に黒ずくめの男の形を捉える。
「もう一つは、あんたが教えてくれた『未来の見える』ダチが、あんたの間合いにいたことだ」
「まあ、なんだかぎりぎりセーフ、と言ったところではあるかな?」
煙幕の消えた中で、黒ずくめの側にいるもう一つの小柄なシルエットを浮かびだした。
足元はどこかおぼつかないように、黒ずくめの男の背後にもたれかかるようにして現れた少年。
もたれた男の肺にラフィが初撃に投げつけた投げナイフが突き立てられていた。
そして、刺した刃をそのままに男から離れ、ラフィの側まで行くカイル。
「…出来れば、さっそく私の力を期待せず、前もって打ち合わせが欲しかったよ」
「うるせぇ、そんな時間も、余裕もあったら、この親父に勝てるか」
そうして二人は鋭く黒づくめの男に視線を投げる。
男は立っていた。まるで刺さった刃などモノともしないように。
「おい…、俺の剣なんて持って」
「さすがに無いから、無理だから。ところで君のとこのボス、不死身か何かかい?」
「…かもしんねぇ」
男は二人を見下ろしたまま、己に打ちつけられている其れを引き抜く。
刃で押さえられていた血が瞬く間に滴り落ちるが、それすらも意に介さぬようにただ二人を見下ろしていた。
「まさか他人にこの俺を仕留めさせるとはな、そんな腑抜けた考えを教えたつもりは無いぞ」
「テンドウ…」
「くだらんな、くだらん」
引き抜いた傷から、血が止まっているわけではない、むしろ湿気った石畳にみるみる間に血溜りが広がっている。
だが、男の生気はまったくかわらず、そのままの強い視線でカイルとラフィを見、そして腰の剣を引き抜いた。
「ここで俺を倒しても、王子を暗殺した罪でお前はこの国に処刑されるぞ、ラフィ」
「だろうな」
「ふん、覚悟の目だな。そんなところだけは一丁前に俺の教えを守ってる。くだらんガキだ」
投げ捨てた言葉と同じに、テンドウが引き抜いた剣をラフィに放った。
「俺の剣…っ!」
剣を受け止めて、驚愕し、呆然とラフィはテンドウを見た。
しかし、そこにあるはずのテンドウの、漆黒の男の姿は無かった。
「テンドウ!?」
姿の無いテンドウに呼びかける、すると何も無いはずの場所から声だけが、テンドウの声だけが石牢に響いた。
『好きにしろ』
其れだけを残して、黒衣の暗殺者は消えた。
8.
「終わった、のか」
「そうだね」
剣を持ったまま、立ち呆けてるラフィとは違い、毒をくらい、暗殺者にボコボコにされ、満身創痍のカイルは、そのままへたり込み、そして床につっぷした。
「正直、今回はしんどかったあ」
「………」
ラフィは答えない。ただ状況だけは冷静に見て取れた。
血溜りに濡れた牢、弱りきって倒れこんでいる王子、そして、自分の腕には、あの日、王子を暗殺しようと入り込んだ時にも手にしていた己の剣。そして…
『好きにしろ』
彼の男の言葉。
「はは、ボロボロだ。これじゃあ侍女達をまた困らせてしまうなあ」
「………」
言葉が、見えない男の言葉が頭の中で木霊する。
「でも、やっぱりちょっと疲れた。…少し眠るよ」
「………」
格子にもたれかかる金の髪の王子。本当に安らかな表情で、息をついて、瞼を閉じた。
本当に無防備にさらされている身体。
ラフィは両膝をついてその表情を、そおっと覗き込んだ。
安定した息遣い、毒気は完全に引いているのだろうが、疲労の残る顔はまだ青白い。
手元にある剣を見る、たった一突きでこの少年の息を根を絶つことの出来る武器だ。
「なあ、お前どこまで『見えて』るんだ…」
先見の王子、己の死までを生まれながらに『識る』少年。
「信じるって、なんだ?」
暗殺者として生きた自分。生まれてすぐに他人の死にまみれて生きてきた己。
「わかんねぇ。わかんねぇよ、やっぱり」
生まれる前から繰り返されてきている戦。こんな戦いばかりの時代に、いつか終わりが来るのだろうか。
「俺は…」
「どうして君は、私があの男と差し向かうと思ったの?」
ラフィはハッとして、カイルを見た。
格子にもたれているカイルは瞼を閉じたまま、言葉だけを紡いだ。
「あの暗殺者が言ったよね、私の『見える』範囲は全てじゃないって、なのに君は私が動くと思っていた、どうして?」
「それは…わかんねぇ」
クスクスとカイルが笑う声が聞こえて、ムッとする。
「ほら、こんなものだよ、信じるなんて」
案外、気がつかないだけで簡単なんだ。と笑いながら言う。
そして、ひとしきり笑ったあと、目を閉じたまま、囁くように呟いた。
「『はじめよう』と私は君に言ったよね」
その言葉をラフィは始め思い出せなかったが、しばらくボウとカイルを眺めて、ようやく初めて会った時、カイルが発した言葉だと気づいた。
それに気づいたようにカイルが後を続けた。
「ここからはじめよう、と。私は言ったね。私は、こんな時代をとっとと終わらせたい、こんなだれもが目減りしながら生きる時代は終わらせるべきだと思う」
「カ…イル」
呼びかけに、カイルの瞼が上がる。覗き込んでいたラフィと目が合う。
「私は王になる。君は……まあ何でもいいけど、私の側にいて一緒にこの大陸の行く末を見て欲しい」
「俺はここに留まれば、処刑されて終わりだ」
「君が生きたいと望むなら、私が君を守るよ」
「んな、女々しい真似出来るか!…っくそ」
ラフィは格子から身体を離すと握り続けていた剣をカイルと己の間に突き刺した。
「くれてやる。お前が俺を守るなら、俺もお前を護る」
「ラフィ…」
カイルは身を起こすと、突き立てられた剣を引き抜いた。
細身の割に、子供が持つには重過ぎるように感じる剣だ。
「この剣に鞘は無いのかい?」
「生まれてこの方、収める鞘なんて持ったことねぇ」
「そうか…」
刀身は鋭く光り、格子から覗く月の光を反射して、まるで細い月のように輝いていた。
「剣になってやるよ。あんたを護る剣に。俺も、見てみたい、カイルの言う時代を」
「うん」
剣と格子の狭間に、ラフィとカイルは見合い。カイルが微笑んだ。
「それじゃあ、終わりをはじめよう。私たちの手で」
石畳の牢で、ラフィと月と剣だけが。その言葉を受け取った。
第零章 了
H21.9.26 改稿
|