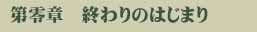
二、
5.
細い月が格子越しに覗き込んでいた。
瞼を開いた少年の目には、あいも変わらず、繋がれたままの両手の枷。
床に視線を落とせば、硬いばかりの湿った石畳。
そして、キィと音を軋ませて、闇の中へ訪れてきた顔にうんざりとした視線を注いだ。
「またあんたか…」
「やあ」
簡単な返事を返した金の髪の少年は、いつものようにこちらの殺気など何もないかのようにツカツカとこちらの格子の側までやってきては、そこにしゃがみこんだ。
しかし、しゃがみこんだカイルの普段とは違う息遣いに、少年が格子の先で身じろぎした。
「おい…お前…もしかして、俺とおんなじ」
「こないだも言ったろう、私の父はロクデナシなんだ。実の息子に毒を盛る程度には、ね」
そう言い切ったときに、彼は格子に身を任せるようにもたれこんだ。
その姿に、あっけにとられたのは一瞬で…、一瞬後には金の髪の王子に少年が噛み付くように怒鳴った。
「ばっ……!お前、馬鹿か!!俺に解毒剤よこすくらいなら、自分の分くらいとっとけ!」
そう言って、枷のついた両の手で握っていた空になった豆菓子の袋をカイルにたたきつけた。
カイルはその袋をしばしじっと見つめると、笑って「よかった」とつぶやいた。
「もしも気づかず捨てられていたらどうしようかと、思っていたよ」
「…お前、俺の話し聞こえてねーのか?」
唸るが効果はない。それどころか、少しばかりカイルの目が見開かれた。
「驚くなあ、私を殺しに来たのは君も、だったよね。なんで私の心配してくれるのかな」
「だ、だれが、心配した!いつ!?俺はお前の間抜け振りを罵倒しただけだ!」
「はは、心配しくれてありがとう。でも大丈夫だよ、今回みたいな為に、今、耐性を付けている途中だからね、まあしばらく見苦しいかもしれないけど」
そうして、もたれかかっていた格子を支えに、カイルがゆっくりと身体を上げる。
「おい、なに考えてんだ」
少年が投げかけた言葉はカイルに対してである、しかし、意識は別の方を向いていた。
その意味を察していたカイルは少し苦労して笑みを作り、ゆったりとした己の装束の裾から扇を取り出す。彼の腕の二の腕程ある扇を一度開き、風をひとなでするように仰いだ後、その精緻な作りの細工とは裏腹に、ガチリとした手ごたえをもって、閉じた。
「鉄扇か…」
「私の父はね、それはそれは人の嫌がることが大好きな人だ。今晩の夕食にもった毒くらいで私をどうこうするつもりはない、むしろ私を動けないようにして、企むようなことなんて、今のところ一つしか――」
言い終える前だった。
薄闇を切り裂くような鋭い刃が、格子に隙間からのぞく枷に縛られた少年の喉下へ向かう。
しかし、その刃の切先を鉄扇で返したのは、金の髪の少年。
弾かれたそれは、石畳に打ちつけられ、鈍い金物の音を出して、落ちた。投げナイフだ。
「おいっ!」
その行動が自分を庇っての事だと気づいた黒髪の少年が怒鳴る。しかし、そんな怒声も意に介さず、息も切れ切れで、次に襲う刃も薙いだ。
しかし、捻った身体の反動ですぐにまた、格子にしがみついて立つような体制になるカイル。
いまだ、身体から毒が抜け気っていない証拠だろう。
「なんで、お前が俺を助けるんだ!?」
「君が死ぬつもりだから」
飛び道具が無駄と判じたのか、薄い闇に黒い大きな体格の男が視界に写された。
カイルは、再び体制を整えると、鉄扇をたたみ、棒状にさせると、腰をひくく落とし、黒いその男に対峙する。
整わない息を、無理やり深呼吸で押さえ込む。
「君が、ここで死ぬことを望んでいるから、それを私は許さないから」
もとより、体格が二倍ちかくある上に、カイルが対峙しているその男は、考えるまでもなくこの手合いのプロだろう。 小手先の剣戟ならいざ知らず、真っ向からカイルが立ち向かったとすれば、結果など見えている。
「勝手なこと言うな!お前が俺の何を知って、んなこと言ってんだ!」
格子越しにこちらに蹴りを食らわせる少年。しかしそんなことで、彼とカイルを隔てているそれが、破れるわけがない。
それをあきれた様に見ると、カイルは苦笑して黒い男に向き直る。
男のこぶしが先ほどの刃とは比べ物にならないほど、重量をもってカイルの前に繰り出された。
真っ向から受けるべきではない。よろめくようにして屈んだカイルはなんとか拳を避け、鉄扇を膝へめいっぱいの力でたたき込んだ。
「嗚呼・・・、やっぱり聞かない、よねぇ」
投げナイフの軌道をそらす程度とは話が違うのだろう、たかだか10歳かそこらの腕力で打たれたものなど意に介す様子はない。
男は鉄扇ごと、足下にいるカイルをただ蹴飛ばした。
「ぐぅっ…!」
「おいっ!?」
蹴飛ばされ、格子にたたき付けられたカイルに寄り、怒鳴りつける少年。
「この程度で俺を助けて、お前が死ぬ気か!?冗談じゃねぇっ、お前を殺しに来た暗殺者だぞ、俺は!見捨てろよ!なんでそれができねぇ!?」
金髪の王子を心配して投げかけた言葉ではない。
ただ純粋に不思議で仕方なかった。
たった、数日しか会っていない、それも己を殺しにやってきた殺し屋をなぜそうも守ろうとするのかが、腹が立つくらい理解できなかったのだ。
耳元で怒鳴る声に少しだけ口角を上げて、咳き込みながら再び立ち上がるカイル。
そして扇を構えると、楽しそうな声音で、つぶやいた。
「私が生を受け、生まれて始めて『見た』ものが君だった」
「は?」
「その時からね、ずっとずっと会ってみたいと思っていたんだ」
「ちょっとまて…なにを」
「その時からね、ずっとずっと『友』になろう、と決めていたんだ」
「・・・・・・・・・」
「私は、私の友人を守る。そんなことに理由なんていらないだろう?」
そうして、カイルは少年に笑った、が、そのカイルの身体が宙に浮く。
「そうか、額の宝玉…、お前が『先見の王子』か」
浮いた、のではない。黒づくめの男がカイルの胸倉をつかみ上げていたのだ。
カイルが気づき、もがいて逃れようとするが、それを気にもせず、子供一人をつかみあげたまま、男は牢に縛られた少年を見下ろした。
「なんとも奇妙な者に懐かれたようだな、ラフィ」
「…その声、テンドウか?」
薄闇のなか、黒尽くめの男を凝視するラフィと呼ばれた少年。
ラフィにとって、多少の闇など視覚を妨げるようなことはないが、それでも黒ずくめの装束に身を包まれた男に、自分の記憶する男との相似を探しても、あまり見つかりはしなかった。しかし、おそらくそうなのだろう。気配やしぐさなどいくらでも変えられる。
「頭領のあんたが俺の始末をしに来たのか、どういう気まぐれだ?それともあんたなりの義理人情のつもりか」
ラフィの問いかけに、テンドウはカイルを石畳に投げ捨て、格子越しに向かい合った。
懐から鉄串を取り出して、ラフィに放つ。
「……」
無造作に伸ばされて、肩でザンバラになっているラフィの髪が一房落ちる。
「気まぐれはお前を拾った一度だけ、義理や人情など俺にあると思うのか?ただお前は、組織の掟にしたがって死ね」
その言葉にラフィの表情は落胆の色はなかった。むしろ、「しょうがない」というような苦笑を浮かべ、ただ立ち尽くした。
そして、目を伏せる。
テンドウはそれを見下ろすと、無造作に地面で気絶したカイルを再びつかみあげ、ラフィの格子越しの足元に落とした。
その鈍い音に気づき、ラフィが目を開くと、己の足元で荒い呼吸を続けるカイルの姿を見、テンドウを見上げる。
「殺せ。己の仕事を全うし、始末をつけてから、俺に殺されろ」
「それは…」
「何を惑っているのか知らんが、この王子を生かしておけば、戦乱はいつまでも終わらない。この国が滅びるまでな。それがこの『先見の王子』の運命だ」
「『先見の王子』?そう言えばさっきも言ってたな、なんなんだそれ」
闇のなかで気絶している王子の顔は存外息が荒いものの、安らかな表情だった。
体内の毒気に大分慣れてきているのだろう。それにしてもこの表情一つ見ても、いままでの彼の王子の能天気ぶりをみても、どこをとってもそんな物騒な運命を背負うような少年に見えない。
「生まれながらにして、この子供は己の生の最期まで、全てを『見て』生きている、『未来視』の能力を持つ人間。そして、預言者に『滅び』の災厄を予言された人間だ。この事実を知るものはごく僅かの人間だけだがな」
「未来…、そんなものをこいつ見えてるのか?」
「さあな、少なくとも全ての未来を『見える』わけでも、知りたい先を『見る』わけでもないようだな。でなくば、ここで転がっているのは私だろう。真実など分かるものか」
「だったら…」
「真実など知ったことか、俺たちにとってはただの仕事の相手かそうでないか、それだけだ」
ラフィにダガーを投げつける。
鞘に納まったままのダガーはラフィの手に吸い付くように収まった。
「理由が必要なら幾らでもつけてやる。この戦乱を終わらせたくはないのか、お前はお前のような、いらぬ孤児を増やしたいと思っていないのだろう。この王子は災厄だ」
そう言ってテンドウがカイルの金の髪をつかみ上げ、喉もとをラフィに突きつけるように持ち上げた。カイルが僅かに唸る。
ラフィは瞳を伏せて、ダガーを鞘から抜く。闇色を吸い込むように、剣先が石牢に溶け込む。
手枷のついた腕と足で王子ににじり寄る。そして、ダガーの持つ手を構える。
「ラ、フィ?」
己の名前を呼ぶ声に我知らず、ビクリとなり、金の髪の王子をみた。
ラフィが何をするのか分かっているはずだ、それなのに、表情はいつもの能天気なそれのままに見えた。
「やっと、名前きけたね」
「あ…、お、お前馬鹿かっ!俺が何するか知って…」
「大丈夫だよ、君は私を殺さない」
やはり能天気なその言葉にカチンと来た。
「暢気だな、それもお前には『見えて』るっていうのか?」
嘲るように笑い、ラフィはダガーをカイルの喉もとに突きつけた。
剣先が彼の薄皮に薄く刺さり、赤いしずくが闇色のダガーに色づく。
「違うよ」
笑って、穏やかに笑ってラフィを見つめた。
「信じてるだけだ」
笑うカイルにつられるように、ラフィも笑んだ。
「ああ、そうかよ」
そしてラフィはダガーを放った。
|