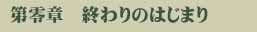
一、
その日は、やけに赤い月の夜だった。
ただ、いま目の前にいる少年には関係のない事なのだろう。
私は、ふとそんなことを考えながら抜き身の剣の切先をこちらに向け、静かな殺気を放つ彼に微笑んだ。
「ずっと」
私の言葉に反応して、ぴくりと眉を動かし、こちらを見据えたのは、褐色の瞳。
「ずっと、待っていたよ」
少年の相好は崩れない。構えた切先も寸分も狂いなく私の喉元に向けられている。
だがかまわない。私は、構わなくていいことを知っている。
「ここから、はじめようか。私の、最初で最後の友よ」
1.
かつて、大陸で一人の王が暗殺された。
一人の王の命が引き金となり、隣国との抗争がはじまり、それは次第に拡大し、気づけば大陸全土を巻き込む戦争が始まった。
人々は争い続け、憎み、女子供ですら、ただ毎日、戦の道具として使われる、そんな国も少なくは無かった。
大陸大戦―――。
後に歴史上そう呼ばれることになるこの大戦は、13年たった今でもなお続いている……
2.
重い、全身が鉛のように重い。
眉根を寄せて、むりやり閉じさせられていた目を開ければ、薄闇とそれについて回るような湿った空気。
周りは石畳に囲まれ、それでも僅かにある格子からは、赤い月が覗いて、完璧の闇を淡く濁らせていた。
そして、己の両手足に鉄の感触を確かめ、それに向けてけちをつけるように唾棄をする。
牢に押し込めるまでに、これでもかと痛めつけられたせいか、はき捨てた唾に血が混じっている。
ますます気を悪くして、少年が口をひん曲げた。
(しくじった…のか?俺が、あんなひょろいガキ一人相手に…)
いくつかやられている肋骨の痛みよりも、その事実が少年の意識を揺るがしていた。
それでも、横倒しになっていた体を起こして石畳に肩を預け、おざなりにされた夜色の髪をくしゃりとかき回すと、少 年は寄せていた眉根を緩ませて、どこか呆けたような、それでいて年相応の、まるでただの10歳の子供のようなあどけない表情でつぶやいた。
「人を…殺りそこなったのは……初めてだ」
そして、彼の標的だった少年を思い出す。
無防備にも誰も警護に付けもせず、まるで自分が来ることを予想していたかのように、ただ、王城の中庭で静かに 佇んでいた、自分と変わらぬ年の金の髪の王子。
まるで、『暗殺者』の自分が来ることを待っていたかのように―――。
(ずっと、待っていたよ)
金の髪の少年はそんなことを自分に向けて言い放った。
ずっと昔からの旧友を迎えるような笑みで。
「どういうことだ?」
まったくさっぱり、訳が分からない。
「初対面…だよなあ?」
どんなに頭をひねったところで、金髪の少年の顔など記憶からは引き出されない。
それもそのはずである。そもそもある訳がないことくらい、思い出そうとしなくても分かる。
あの王子と『暗殺者』の己に何一つ接点などある訳がないのだ。
過去も、今も、そしてこれからも―――。
鉄の鎖と血のにおいに、再び眉根を寄せて、皮肉った笑みをつくる。
「俺もここまでか」
思えば短いような、いやおそらく普通の環境で育った子供ならば短いと人に言われる年頃なのだろう。しかし、彼はそうは思わなかった。数多くの同胞の死を見すぎていたためか、ただ、死が身近にすぎたためか。それは、まあどちらでも構わなかった。
どちらかなど関係なく…
「直に処刑される俺なんかには、もう、二度とあのお坊ちゃんとは会うことも無いっていうことだ」
実に、軽い調子でつぶやくと、その体を横にして眠りについた。
3.
「暗殺者を捕らえたという報告は聞いた。なぜ、その場で処刑をせぬ、カイル」
「父上、相手は子供でした」
「…だから、どうだと言うのだ」
王の謁見の間で、膝をついて、臥せたままでカイルは苦笑をした。
我が父親ながら、相変わらずの外道っぷり。
その言葉も、息子を思っての言葉ならば分からなくはないが、だが、この父親の外道ぶりはそんなかわいらしいものではない。
「父上、それは、“すぐに殺さなければならない理由”がおありのように見えますよ。子供は元来、私のように正直なもの、問いただせば暗殺の依頼者が分かるかもしれません」
「お前が正直者だと。よくもぬけぬけと…。中庭で、相当の兵を隠し、あの暗殺者を捕縛したそうだな。お前、また『見た』のか」
「なんのことでしょう、子供の私にはついぞ理解できません」
「食えぬやつめ、件の暗殺者が何を口走ったところで、私には何もお前に臆する所などない」
「そうでしょうとも、ですから私はそのようなことはしません。うちの家臣をこのようなことで失いたくはありませんから」
「お前の家臣ではない。私のだ。それに、そのような“暗殺”をもくろむようなものにまで、温情をかける意味はないだろう」
「ええ。とんだ濡れ衣でなければ、ね」
そう言うと、カイルは膝をはなし、王前に背をむけた。禁色の真紅のマントを翻して。
「たしかに、家臣は私の物ではない。ですが…、あれは私のものです。彼の暗殺者の命は私に預けさせていただきます」
「カイル!」
背を向けたカイルに怒号と憎しみに満ちた声が届く。
カイルは振り向いた。とてもやわらかく、慈愛に満ちた笑みで。
「はい、父上」
憎しみの瞳をその笑顔で受け止める。
「いつか、いつか貴様を…っ!」
「無理です。父上」
きっぱりと言い放ち。
カイルは再び謁見の間の扉に向かうため、父王に背を向ける。
「とても残念ですが。私には『見えて』います。貴方は無理だ」
そして、閉ざされた扉の向こうで、王の錫丈が叩きつけられる音が響いた。
4.
「というわけでね。まあ、うちの父親も困ったモンだと思わない?」
「あーのーなぁ。なんでっ!お前が!ここにいるんだ!」
牢の柵の向こう側で豆菓子を携えてこちらに話しかける少年。たしか記憶違いでなければ、このメイトロークとかいう国の王子だったはずだ。
金の髪に緑眼。額にはぴたりと嵌った石飾りがキラキラと揺れている。
「なんでって、…ふぅーむ。………うん。遊びにきた、かな?」
「あ、頭いてぇ。どこの世界に、殺しにやってきた奴相手に遊ぶ奴がいるかっ!」
牢屋越しでは何か出来るわけではないが、噛み付くように怒鳴りつける。
ここ数日、ことあるごとにここにやって来ては、他愛もない世間話をしてゆくこの変人にあきれ返っていた。
初めてここを訪れた少年をみたとき、彼は今度こそ己の死を覚悟していたのだ。なのに、来る日も来る日も、やってきてはくだらない話ばかりを持ち込むだけで、一向に己にたいして何をするでもなかった。
「ところで、まだ名前も話す気はないのかい?」
「さあな」
「じゃあ、年は?私と変わらないと思ってるんだけどなあ」
「さあな」
「ふぅん、ところでキミ、女顔だとか言われたりしない?」
「…こっち顔貸せ、喉食いちぎってやる」
枷を格子に打ち付けて、このすっ呆けた王子を威嚇する。
カイルは少しだけ肩を竦めると、豆菓子をにらみつける少年に押し付け、牢から離れた。
「機嫌をそこねたかな。それじゃあ、また来るよ」
「なんなんだ!?いったいこれはなんなんだーっ!!」
ガシャンと石畳に打ちつけた手枷が派手に鳴るが、決して取れるわけではない鎖。ご丁寧に足にも同じ金音を鳴らすそれがある。
腹立たしいがどうすることも出来ず、少年はカイルが置いていった豆菓子を視界に入れる。
「ふん、こんなガキの食い物でおれが誑かされると思ったら、大間違いだっての」
自分もガキだという事を棚に上げ、その割には口元を緩ませて、そそくさと豆菓子の袋を手に収める。
ぱくりと一つほお張り、何度か租借するように口を動かした。
そして、視線は已然豆菓子から動かしはせず、ただ動かしている口だけは不敵な笑みに変じていく。
「まあ、気の利いた差し入れだな」
そして、我知らず変じた笑みに気づき、苦虫を噛み潰した顔に戻すと。
繋がれた鎖で頭を抱えて、呻いた。
「やっぱり意味がわかんねぇ。なに考えてんだあのガキ」
直に、看守からも夕食が運ばれてくるだろう、それまでにはこの豆菓子を食ってしまわないと、あとでいろいろ厄介だろうと、少年は袋の中身を直接口の中へ放り込む。
豆菓子を食みながら、先ほどまでいた王子の真意を考えようとしたが、腹が満たされたのか、考えているうちに瞼は落ちていった。夕食を持って来た看守にたたき起こされるまで、目を開くことはなかった。
|